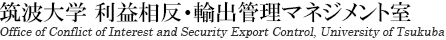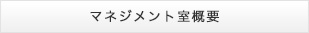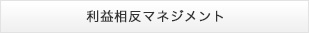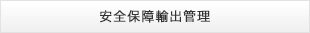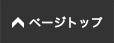未分類
未分類
安全保障輸出管理のための特定類型自己申告書・誓約書の提出のお願い/Request for submission of the Self-Declaration on Specific Categories form and Pledge forms for Security Export Control
2022.10.06最新の内容はこちらに移動しましたhttps://coi-sec.tsukuba.ac.jp/export_control/pledge/
入学/卒業(修了)等にあたって必要な手続き
Required Procedures for Admission or graduation etc.
安全保障輸出管理のための特定類型自己申告書および誓約書提出のお願い
安全保障に関連する機微技術流出の防止強化として「みなし輸出管理」の明確化がなされ、関係法令が改正されました(令和4 年5 月1 日施行)。
これに伴い、大学院生・研究生への機微技術の提供の一部が「外国為替及び外国貿易法」(外為法)の管理対象となり、本学大学院への入学者全員に対して、特定類型の確認を求めることとなりました。ついては、「リーフレット」を参照の上、「特定類型自己申告書」を記入してください。
また、入学時及び修了等時に「外国為替及び外国貿易法」を遵守する誓約書に署名していただきます。様式
Request for Submission of the Self-Declaration on Specific Categories form and Pledges (enrollment or graduation etc.) for Security Export Control
In order to strengthen the prevention of leakage of sensitive technology related to security, “deemed export control” was clarified and related laws and regulations were revised (effective May 1, 2022).
As a result, part of the provision of sensitive technology to graduate students and non-degree Research student(kenkyusei) is now subject to control under the Foreign Exchange and Foreign Trade Law (hereinafter called “FEFTA”),and all (prospective) students to our graduate school are required to confirm a “Self-Declaration on Specific Categories”.
Please refer to the “Leaflet” and submit the” Self-Declaration on Specific Categories” for more information. Also, all students who enroll in the graduate school are requested to sign a pledge (enrollment/employment) to comply with the FEFTA at the time of admission. Formats
対象者:学生(大学院レベル)/ Target :Students(Graduate level)
入学にあたり提出が必要な書類/Required documents at the time of admission
2023年度大学院入学者
●「誓約書(入学時)」
manaba(学習管理システム)から提出してください。
Students who enroll the graduate school in AY2023
●Pledge (enrollment)
Please submit a pledge through manaba.
【manabaコース名/manaba course name】
誓約書(入学時)Pledge(enrollment)/22169
manabaからの誓約書提出のお願い/Please submit a pledge through manaba.
manaba での誓約書の提出状況は学籍番号で管理しているため、学籍番号が変わる場合は、誓約書を再度提出してください。
【Note】
Please submit the pledge again, if your student ID number is changed, as the submission status of the pledge in manaba is managed by the student ID number.
修了(退学等を含む)にあたって必要な手続き
Required Procedures for Graduation (including withdrawal)
誓約書(卒業(修了等))をmanabaから提出してください。
注意)筑波大学(内部)に進学予定の場合は、提出は任意です。進学後の過程を修了する際には、必ず誓約書を提出してください。
We ask you to submit a pledge at the time of graduation. Please register for the following course and submit the pledge via manaba.
Note)If you are going to enter a graduate school of the University of Tsukuba, you don’t need to submit it this time, but after completion in your next graduate school, please submit a pledge via manaba.
【manabaコース名/manaba course name】
誓約書/Pledge(修了時/graduation ) /23114
manabaからの誓約書提出のお願い/Please submit a pledge through manaba.
説明動画/Explainer video
こちらの動画で、提出の必要性について解説しています。
Please watch this explainer video for the documents you need to submit.
用語解説/Description
<大学・研究機関における「技術の提供」や「貨物の輸出」の機会(23)の例>
| 技術提供等の機会 | 具体例 |
| 留学生・外国人研究者の受入れ | ○実験装置の貸与に伴う提供 ○研究指導に伴う実験装置の改良、開発 ○技術情報をFAXやUSBメモリを用いて提供 ○電話や電子メールでの提供 ○授業、会議、打合せ ○研究指導、技能訓練 等 |
| 外国の大学や企業との共同研究の 実施や研究協力協定の締結 |
○実験装置の貸与に伴う提供 ○共同研究に伴う実験装置の改良、開発 ○技術情報をFAXやUSBメモリに記憶させて提供 ○電話や電子メールでの提供 ○会議、打合せ 等 |
| 研究試料等の持出し、海外送付 | ○サンプル品の持ち出し、海外送付 ○自作の研究資機材を携行、海外送付 等 |
| 外国からの研究者の訪問 | ○研究施設の見学 ○工程説明、資料配付 等 |
| 非公開の講演会・展示会 | ○技術情報を口頭で提供 ○技術情報をパネルに展示 等 |
(23)このほか、オンラインでの講義、会議、打合せ等についても「技術の提供」の機会となり得ることに注意が必要です。経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第四版」 p.27(2022年9月22日 閲覧)より書き起こし
<Examples of Opportunities for Transfer/Export of Technologies/Goods in Academic and Reseach Institutions(23)>
| Occasions | Specific examples |
| Accepting international students/researchers | – Transfer of technologies in lending the experiment devices – Enhancement/development of the experiment devices associated with research instructions – Providing technical information using fax or a USB drive – Providing such information through phone calls or email – Classes, meetings or discussions – Research instructions or training |
| Execution of a joint research or the collaborative agreement with a foreign university/company | – Transfer of technologies in lending the experiment devices – Enhancement/development of the experiment devices associated with the joint research – Providing technical information through fax or as data in a USB drive – Providing such information through phone calls or email – Meetings or discussions |
| Bringing/shipping research samples overseas | – Bringing/shipping samples overseas – Bringing/shipping self-made research materials/equipment overseas |
| Visits of Foreign Researchers | – Research facility tours – Describing the processes or distributing the handout materials |
| Private lectures/exhibitions | – Verbally providing technical information – Showing technical information on panel |
(23) In addition, care must be taken that on-line lectures, meetings, or talks have a “technology-giving” risk.
Extracted from the material ” Guidance for the Control of Sensitive Technologies for Security Export for Academic and Research Institutions (4th Edition)”,METI,METI, p.27, 22 Sep, 2022
居住者および非居住者の定義
| 居住者 | 非居住者 | |
| 日本人の場合 | ①日本に居住する者 ②日本の在外公館に勤務する者 |
①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 ②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者 ③出国後2年以上滞在している者 ④上記①~③に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者 |
| 外国人の場合 | ①日本にある事務所に勤務する者 ②日本に入国後6か月以上経過している者 |
①外国に居住する者 ②外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 ③外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人(ただし、外国において任命又は雇用された者に限る) |
| 法人等の場合 | ①日本にある日本法人等 ②外国の法人等の日本にある支店、出張所その他の事務所 ③日本の在外公館 |
①外国にある外国法人等 ②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所 ③日本にある外国政府の公館及び国際機関 |
| その他 | 合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等 |
財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」を基に作成
Definition of ”resident”or”non-resident”
| Resident | Non-resident | |
| Japanese | (1)Those who live in Japan (2)Those who work at diplomatic establishments in Japan |
(1) Those who left Japan to work at an office in a foreign country and live (2) Those who left Japan to live in foreign country for two or more years (3) Those who go to a foreign country and stay therein for two or more years (4) Those who meet any of (1) to (3) above, return to Japan temporarily, and stay for less than six months Foreigner |
| Foreigner | (1)Those who work at an office in Japan (2)Those who come to Japan and stay for six or more months |
(1)Those who live overseas (2) Those who provide public service in a foreign government or international organ (3)Diplomatic officials or attendants/employees who work at a consulate(limited to those who are appointed or employed overseas) |
| Corporation | (1) Domestic companies based in Japan (2) Branches, agencies, or other offices of a foreign company in Japan (3) Foreign diplomatic offices in Japan |
(1) Foreign companies based in a foreign country (2) Foreign branches, agencies, or other offices of a Japanese corporation (3) Foreign governments’ offices or international organizations in Japan |
Note:Regardless of the classification above, the US Armed Forces, UN Forces, and constituent members thereof are non-residents.
Definition of ”resident”or”non-resident”
Extracted from the material ” Guidance for the Control of Sensitive Technologies for Security Export for Academic and Research Institutions (4th Edition)”,METI,METI, p.30,22.Sep.2022
外部情報
みなし輸出とは 経済産業省 みなし輸出に関する解説
- 経済産業省 安全保障輸出管理「大学・研究機関」
【English】Guidance for the Control of Sensitive Technologies for Security Export for Academic and Research Institutions (4th Edition) - 経済産業省 「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第四版」(令和4年2月)
- 経済産業省 「大学・研究機関における安全保障貿易管理に関するヒヤリハット事例集(第一版) 」(令和2年1月)(PDF 1.0MB)
- 経済産業省 大学・研究機関向けQ&A(令和3年2月)(PDF 254KB)
TExCO 入力に迷ったら
2022.09.27TExCO入力者は?TExCO提出先は?
| 海外出張する人 | TExCO入力する人 | TExCO提出先 |
| 教員 | ・教員・職員 | 所属組織の事務を所掌する支援室・研究センター等 |
| 学生 | ・指導教員・職員(秘書等) ・代理権を付与された本人 |
支援室またはグローバル教育院 |
| 客員教授・名誉教授 (雇用関係になく、統一認証IDがないが、筑波大学の用務で海外出張する場合) |
・用務を把握している教員・職員 | 経費元(出張経費を管理している支援室・研究センター等) |
こんなとき、TExCO入力に迷ったら…
| 用務地が二か所以上 | 同一の用務(技術の提供)なら1件の申請になります。 | ||
| 用務が二件以上 | 用務(技術の提供)ごとに申請します。 ・同一の用務として扱えるなら一件の手続きで、別の取引先の用務もあるなら申請をわけます。 (一度の出張で学会発表と表敬訪問の組み合わせなど、技術提供の用務がひとつであれば申請は1件で構いません。) |
||
| 携行品とは | 自己使用のノートパソコン、カメラ、携帯電話などは届け出不要。 PC内に研究内容などの技術データが保存されていても提供する目的がなければ届け出不要です。ただしリスト規制に該当するような超ハイスペック品であれば手続きをお願いします。(現地で使用する試薬や調査機材は使用者が自分でも申請が必要) |
||
| 学会参加のみ (発表無し) |
学会名を備考欄に記入し、発表がない旨コメントを記載してください。 | ||
| 先にTRIP入力した | TExCOのリファレンス番号が発番されたらTRIPシステムにログインして該当の申請の輸出管理に入力してください。 (TRIPについての問い合わせはグローバルコモンズへお願いします) |
||
| 提出先を間違えた | 間違って提出してしまった先の部局輸出管理担当者に差戻処理を依頼してください。 | ||
| 申請を消したい | 未提出のものは自分で取下げボタンをおしてください。一度提出してしまった申請は自分では取下げ処理ができないので、部局輸出管理担当者にその旨を伝え、取下げ処理を依頼してください。二重に申請してしまったものも同様にお願いします。 | ||
| 日程が変更になった | 内容や年度が変わらなければ、変更などの手続きは不要です。 | ||
| 先方の経費で出張する | 筑波大学の用務での出張であれば、経費負担に関係なくTExCOでお手続きをお願いします。 | ||
代理権でできること ※注意 部局輸出管理担当者は代理者にはなれません
※代理権で入力されたデータは代理権を付与した教職員も見ることができます。
| 代理者区分 | 海外出張申請 | 留学生受入れ申請 | 訪問者受入れ申請 |
| 代理権を付与された教職員 | ○ | ○ | ○ |
| 代理権を付与された学生 | ○(本人の出張のみ) | × | × |
その他
| 部局輸出管理担当者を二人にしたい | 部局担当者は一部門に複数人登録可能です。 ログインアカウントは個人のものとなりますが、TExCOのお知らせメールの送信先は個人あてでも組織メールも可能です。 |
| 一人の担当者で複数部門を受け持ちたい | 一人の担当者が複数の部門を担当することがシステム上はできませんので、ご事情あればマネジメント室にご相談ください。 |
規制対象となる技術の提供等
2022.09.22<大学・研究機関における「技術の提供」や「貨物の輸出」の機会(23)の例>
| 技術提供等の機会 | 具体例 |
| 留学生・外国人研究者の受入れ | ○実験装置の貸与に伴う提供 ○研究指導に伴う実験装置の改良、開発 ○技術情報をFAXやUSBメモリを用いて提供 ○電話や電子メールでの提供 ○授業、会議、打合せ ○研究指導、技能訓練 等 |
| 外国の大学や企業との共同研究の 実施や研究協力協定の締結 |
○実験装置の貸与に伴う提供 ○共同研究に伴う実験装置の改良、開発 ○技術情報をFAXやUSBメモリに記憶させて提供 ○電話や電子メールでの提供 ○会議、打合せ 等 |
| 研究試料等の持出し、海外送付 | ○サンプル品の持ち出し、海外送付 ○自作の研究資機材を携行、海外送付 等 |
| 外国からの研究者の訪問 | ○研究施設の見学 ○工程説明、資料配付 等 |
| 非公開の講演会・展示会 | ○技術情報を口頭で提供 ○技術情報をパネルに展示 等 |
(23)このほか、オンラインでの講義、会議、打合せ等についても「技術の提供」の機会となり得ることに注意が必要です。
経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第四版」https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf p.27(2022年9月22日 閲覧)より書き起こし
<Examples of Oppotunities for Transfer/Export of Technologies/Goods in Academic and Reseach Institutions(23)>
| Occasions | Specific examples |
| Accepting international students/researchers | – Transfer of technologies in lending the experiment devices – Enhancement/development of the experiment devices associated with research instructions – Providing technical information using fax or a USB drive – Providing such information through phone calls or email – Classes, meetings or discussions – Research instructions or training |
| Execution of a joint research or the collaborative agreement with a foreign university/company | – Transfer of technologies in lending the experiment devices – Enhancement/development of the experiment devices associated with the joint research – Providing technical information through fax or as data in a USB drive – Providing such information through phone calls or email – Meetings or discussions |
| Bringing/shipping research samples overseas | – Bringing/shipping samples overseas – Bringing/shipping self-made research materials/equipment overseas |
| Visits of Foreign Researchers | – Research facility tours – Describing the processes or distributing the handout materials |
| Private lectures/exhibitions | – Verbally providing technical information – Showing technical information on panel |
(23) In addition, care must be taken that on-line lectures, meetings, or talks have a “technology-giving” risk.
Extracted from the material ” Guidance for the Control of Sensitive Technologies for Security Export for Academic and Research Institutions (4th Edition)”,METI,METI, https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03_eng.pdf p.27,22.Sep.2022
居住者および非居住者の定義 Definition of ”resident”or”non-resident”
2022.09.22| 居住者 | 非居住者 | |
| 日本人の場合 | ①日本に居住する者 ②日本の在外公館に勤務する者 |
①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 ②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者 ③出国後2年以上滞在している者 ④上記①~③に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者 |
| 外国人の場合 | ①日本にある事務所に勤務する者 ②日本に入国後6か月以上経過している者 |
①外国に居住する者 ②外国政府又は国際機関の公務を帯びる者 ③外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人(ただし、外国において任命又は雇用された者に限る) |
| 法人等の場合 | ①日本にある日本法人等 ②外国の法人等の日本にある支店、出張所その他の事務所 ③日本の在外公館 |
①外国にある外国法人等 ②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所 ③日本にある外国政府の公館及び国際機関 |
| その他 | 合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等 |
居住者および非居住者の定義
財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」を基に作成
| Resident | Non-resident | |
| Japanese | (1)Those who live in Japan (2)Those who work at diplomatic establishments in Japan |
(1) Those who left Japan to work at an office in a foreign country and live (2) Those who left Japan to live in foreign country for two or more years (3) Those who go to a foreign country and stay therein for two or more years (4) Those who meet any of (1) to (3) above, return to Japan temporarily, and stay for less than six months Foreigner |
| Foreigner | (1)Those who work at an office in Japan (2)Those who come to Japan and stay for six or more months |
(1)Those who live overseas (2) Those who provide public service in a foreign government or international organ (3)Diplomatic officials or attendants/employees who work at a consulate(limited to those who are appointed or employed overseas) |
| Corporation | (1) Domestic companies based in Japan (2) Branches, agencies, or other offices of a foreign company in Japan (3) Foreign diplomatic offices in Japan |
(1) Foreign companies based in a foreign country (2) Foreign branches, agencies, or other offices of a Japanese corporation (3) Foreign governments’ offices or international organizations in Japan |
Note:Regardless of the classification above, the US Armed Forces, UN Forces, and constituent members thereof are non-residents.
Definition of ”resident”or”non-resident”
Extracted from the material” Guidance for the Control of Sensitive Technologies for Security Export for Academic and Research Institutions (4th Edition)”,METI,METI, https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03_eng.pdf p.30,22.Sep.2022
規則・申告書抜粋
2022.07.06○国立大学法人筑波大学利益相反規則(平成17年法人規則第50号)
利益相反規則第10条に自己申告について定められています。
○申告書のダウンロードはこちら
○令和4年度利益相反規則改正に関するQ&A
※申告書に記載されている注意書きから抜粋
1.本様式の「A」(兼業報酬、実施料等、給与)及び「B」(株式等)は、これまでも個人的な利益とされてきたものを意味します。これに対して「C」は、令和4年の改正により新たに追加されたものです。後者について詳細は注13.に記載していますが、企業等から職員等に対して提供される法人の管理下にない金銭、物品若しくは役務等であって職務に関連するもの又は職務の信頼性を損なうおそれのあるものに限定されますので、研究資金、奨励金、賞金、寄附金等のほとんどは対象外となるものと思われます。報告すべき個人的な利益は次のとおりです。
「A」の場合:当該年度中企業等から得るこれらの個人的な利益(兼業報酬、実施料等、給与)が合計100万円以上となることが予定される場合に行い、取り止めや減額のため100万円未満になる場合については提出の必要はありません。(単一の企業等の場合のみならず複数の企業等から個人的な利益を得た結果、同一の年度内にこれらの企業等から得た利益の合計が100万円以上である場合を含みます。)
「B」の場合:株式等に変更のあった場合は、保有数の変更や売却と売却益などについて具体的に記載してください。
「C」の場合:本学の管理下にないものであって職務に関連するもの又は職務の信頼性を損なうおそれのあるものは金額にかかわらず報告してください。
2.定期的報告の対象は前年度分です。翌年度の5月末までに提出します。随時報告(国立大学法人筑波大学利益相反規則第10条第2項)は、「A」(兼業報酬、実施料等、給与)の場合は個人的な利益の金額が当該年度に合計100万円を超えると見込まれる時点で行います。「B」(株式等)及び「C」(法人の管理下にないもので金額の下限なし)の場合は新たに取得した時点で行います。
3.随時報告により既に報告済みのものについては定期的報告で報告の必要はありません。
4.随時報告で報告した企業等における個人的な利益に変更があった場合は、随時報告の自己申告書を訂正のうえ、変更箇所を具体的に記載して随時提出してください(過去に報告した利益の増額や別の種類の個人的な利益の追加等)。
5.企業等1社について1枚に記入してください。
6.企業等が企業以外の国内の公共的機関(国、地方公共団体、大学、独立行政法人等)であるときは、報告の必要はありません。
7.兼業によるものの利益については、国内の診療又は教育兼業に係る報酬を除きます。
8.外部資金職員及び非常勤職員は兼業の承認を得る必要はありませんが、勤務時間及び健康管理の観点から他機関で業務を行う日や時間を申し出てもらう必要があります(兼業マニュアル参照)。当該申出の内容については「A」記載の兼業の欄に記載してください。
9.研究成果の実施料若しくは売却による利益については、国立大学法人筑波大学職務発明規程(平成16年法人規程第5号)第9条の規定に基づき本学により支払われる補償金を除きます。
10.給与の全部又は一部の支払いとは、外部資金職員やクロスアポイントメント制度の利用などにより、給与は本学から支払われるが、原資の全部又は一部が当該企業等のものである場合(クロスアポイントメント制度により企業等から直接給与の全部又は一部を受け取る場合を含みます。)を意味します。
11.「B」の株式等については、未公開株式か公開株式かを問いません。未公開株式の保有の場合は1株以上を対象とし、公開株式の保有の場合は発行済み株式総数の5%以上を対象とします。また、新株予約権、合同・合名・合資会社を包含する持分会社の持分等を含みます。金額等の記入に当たっては、これらの種類を記載するとともに、株式又は新株予約権にあっては株式数を、合同会社等の持分にあっては金額を記入してください。ただし、株式等の発行元企業等と本学との間に受託・共同研究、研究成果の移転、寄附金、物品等購入その他の関係がある場合に限ります。本学と当該企業との関係は知り得る限りすべて記入してください。
12.株式等の保有に限り職員等本人のみならずその配偶者及び生計を一にする一親等内の親族が得た場合も報告義務の対象となっており、この場合は、自己申告書の様式中「株式等の種類・保有数等」の項に、「配偶者○○株」のように、株式保有数等を記入するものとします。
13.「C」の「補助金・助成金等のすべての研究資金」~「その他(具体的に)」までの個人的な利益の種類については、本学の管理下にあるものは除きます。個人的に受領した後に本学に寄附したものについても報告不要です。したがって、特に研究資金や奨励金、賞金、寄附金については本学の研究費に充当しようとする場合は本学学長宛てに寄附して本学事務において経理されるのが通常ですので、そのような場合は報告の対象外となります。これらの研究資金等のうち外国政府・軍やそれらの委託を受けた民間団体等からの提供を受けて仮に私的に経理しているものがあれば、そういうものが報告の対象となってきます。また、出張費や講演料、執筆料については、正式に兼業の届出・承認を受けて出張、講演及び執筆を行いその費用の弁償や謝金を受けている場合は「A」の「兼業によるもの」の欄に記入してください。兼業にあたらない原稿執筆により謝金を受け取った場合については、職務外の行為に対して謝金を受け取ったものであり、「職務に関連するもの」に該当せず、また、このような原稿執筆はそれぞれの分野において長年にわたり広く慣行として行われているので「職務の信頼性を損なうおそれがあるもの」にも該当しないので報告義務の対象外となります。したがって、「C」の「出張費、講演料、執筆料」については上記以外のものであって、かつ、正式の兼業手続によらないものがあれば記入してください。なお、ここでの研究資金等については、国や独立行政法人等からのものはもともと対象外とされており、民間団体からのものであっても受領した教員等から本学に寄附されたものも対象外となります。これら以外の私的に経理されているものであって、職務に関連するもの又は職務の信頼性を損なうおそれのあるものだけが対象となり、「A」の兼業報酬等とは別に、金額の多寡にかかわらず報告しなければならないものとしています。報告すべきかどうか迷ったときは利益相反・輸出管理マネジメント室に相談してください。