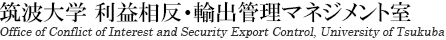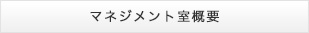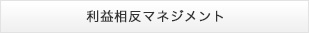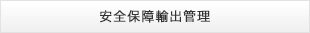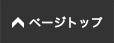新着情報
新着情報
規則・申告書抜粋
2022.07.06○国立大学法人筑波大学利益相反規則(平成17年法人規則第50号)
利益相反規則第10条に自己申告について定められています。
○申告書のダウンロードはこちら
○令和4年度利益相反規則改正に関するQ&A
※申告書に記載されている注意書きから抜粋
1.本様式の「A」(兼業報酬、実施料等、給与)及び「B」(株式等)は、これまでも個人的な利益とされてきたものを意味します。これに対して「C」は、令和4年の改正により新たに追加されたものです。後者について詳細は注13.に記載していますが、企業等から職員等に対して提供される法人の管理下にない金銭、物品若しくは役務等であって職務に関連するもの又は職務の信頼性を損なうおそれのあるものに限定されますので、研究資金、奨励金、賞金、寄附金等のほとんどは対象外となるものと思われます。報告すべき個人的な利益は次のとおりです。
「A」の場合:当該年度中企業等から得るこれらの個人的な利益(兼業報酬、実施料等、給与)が合計100万円以上となることが予定される場合に行い、取り止めや減額のため100万円未満になる場合については提出の必要はありません。(単一の企業等の場合のみならず複数の企業等から個人的な利益を得た結果、同一の年度内にこれらの企業等から得た利益の合計が100万円以上である場合を含みます。)
「B」の場合:株式等に変更のあった場合は、保有数の変更や売却と売却益などについて具体的に記載してください。
「C」の場合:本学の管理下にないものであって職務に関連するもの又は職務の信頼性を損なうおそれのあるものは金額にかかわらず報告してください。
2.定期的報告の対象は前年度分です。翌年度の5月末までに提出します。随時報告(国立大学法人筑波大学利益相反規則第10条第2項)は、「A」(兼業報酬、実施料等、給与)の場合は個人的な利益の金額が当該年度に合計100万円を超えると見込まれる時点で行います。「B」(株式等)及び「C」(法人の管理下にないもので金額の下限なし)の場合は新たに取得した時点で行います。
3.随時報告により既に報告済みのものについては定期的報告で報告の必要はありません。
4.随時報告で報告した企業等における個人的な利益に変更があった場合は、随時報告の自己申告書を訂正のうえ、変更箇所を具体的に記載して随時提出してください(過去に報告した利益の増額や別の種類の個人的な利益の追加等)。
5.企業等1社について1枚に記入してください。
6.企業等が企業以外の国内の公共的機関(国、地方公共団体、大学、独立行政法人等)であるときは、報告の必要はありません。
7.兼業によるものの利益については、国内の診療又は教育兼業に係る報酬を除きます。
8.外部資金職員及び非常勤職員は兼業の承認を得る必要はありませんが、勤務時間及び健康管理の観点から他機関で業務を行う日や時間を申し出てもらう必要があります(兼業マニュアル参照)。当該申出の内容については「A」記載の兼業の欄に記載してください。
9.研究成果の実施料若しくは売却による利益については、国立大学法人筑波大学職務発明規程(平成16年法人規程第5号)第9条の規定に基づき本学により支払われる補償金を除きます。
10.給与の全部又は一部の支払いとは、外部資金職員やクロスアポイントメント制度の利用などにより、給与は本学から支払われるが、原資の全部又は一部が当該企業等のものである場合(クロスアポイントメント制度により企業等から直接給与の全部又は一部を受け取る場合を含みます。)を意味します。
11.「B」の株式等については、未公開株式か公開株式かを問いません。未公開株式の保有の場合は1株以上を対象とし、公開株式の保有の場合は発行済み株式総数の5%以上を対象とします。また、新株予約権、合同・合名・合資会社を包含する持分会社の持分等を含みます。金額等の記入に当たっては、これらの種類を記載するとともに、株式又は新株予約権にあっては株式数を、合同会社等の持分にあっては金額を記入してください。ただし、株式等の発行元企業等と本学との間に受託・共同研究、研究成果の移転、寄附金、物品等購入その他の関係がある場合に限ります。本学と当該企業との関係は知り得る限りすべて記入してください。
12.株式等の保有に限り職員等本人のみならずその配偶者及び生計を一にする一親等内の親族が得た場合も報告義務の対象となっており、この場合は、自己申告書の様式中「株式等の種類・保有数等」の項に、「配偶者○○株」のように、株式保有数等を記入するものとします。
13.「C」の「補助金・助成金等のすべての研究資金」~「その他(具体的に)」までの個人的な利益の種類については、本学の管理下にあるものは除きます。個人的に受領した後に本学に寄附したものについても報告不要です。したがって、特に研究資金や奨励金、賞金、寄附金については本学の研究費に充当しようとする場合は本学学長宛てに寄附して本学事務において経理されるのが通常ですので、そのような場合は報告の対象外となります。これらの研究資金等のうち外国政府・軍やそれらの委託を受けた民間団体等からの提供を受けて仮に私的に経理しているものがあれば、そういうものが報告の対象となってきます。また、出張費や講演料、執筆料については、正式に兼業の届出・承認を受けて出張、講演及び執筆を行いその費用の弁償や謝金を受けている場合は「A」の「兼業によるもの」の欄に記入してください。兼業にあたらない原稿執筆により謝金を受け取った場合については、職務外の行為に対して謝金を受け取ったものであり、「職務に関連するもの」に該当せず、また、このような原稿執筆はそれぞれの分野において長年にわたり広く慣行として行われているので「職務の信頼性を損なうおそれがあるもの」にも該当しないので報告義務の対象外となります。したがって、「C」の「出張費、講演料、執筆料」については上記以外のものであって、かつ、正式の兼業手続によらないものがあれば記入してください。なお、ここでの研究資金等については、国や独立行政法人等からのものはもともと対象外とされており、民間団体からのものであっても受領した教員等から本学に寄附されたものも対象外となります。これら以外の私的に経理されているものであって、職務に関連するもの又は職務の信頼性を損なうおそれのあるものだけが対象となり、「A」の兼業報酬等とは別に、金額の多寡にかかわらず報告しなければならないものとしています。報告すべきかどうか迷ったときは利益相反・輸出管理マネジメント室に相談してください。