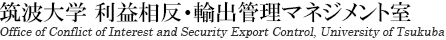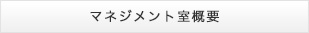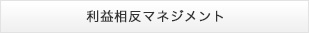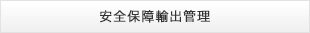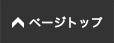許可を要しない役務取引等(許可例外)
許可例外 例外が認められると思われるケースでも必ず事前確認が必要です。
貿易外省令第9条において、許可を必要としない技術提供が規定されています。
例外規定に当たる場合は、提供する技術がたとえリスト規制技術であっても、許可を取得する必要はありません。ただし例外規定の適用を個々の教職員等の判断に委ねることは法令違反につながる可能性があります。許可例外が適用できると考えられる場合でも、確認シートを提出し、事前確認を行ってください。
| 貿易外省令第9条第2項 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 第9号 | 公知の技術※1 | 詳細下記 |
| 第10号 | 基礎科学分野の研究活動※2 | 特定の製品への設計、製造を目的としないもの |
| 第11号 | 工業所有権の出願・登録 | |
| 第12号 | 必要最小限の使用の技術 | 貨物の輸出に付随。プログラムは除く |
| 第13号 | 必要最小限の使用の技術 | プログラムの提供に付随。プログラムは除く |
| 第14号 | 市販のプログラム |
※1公知の技術とは
公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引であって、以下のいずれかに該当するもの
-
- イ新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、 既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引
- ロ学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
- ハ工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
- ニソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
- ホ学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引
※2基礎科学分野の研究活動とは
「自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、理論的又は実験的方法により行うものであり、特定の製品の設計又は製造を目的としないもの」をいいます。
※例えば、以下のようなケースが対象となると考えられます。
・宇宙の生成過程に関する研究
・素粒子理論に関する研究 等
※上記のような「自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動」であっても、特定の製品の設計又は製造を目的とするものである場合は、「基礎科学分野の研究活動」に該当しないので、注意が必要です。
※同様に、特定の製品の設計又は製造を目的としない研究活動であっても、「自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動」でない限り、「基礎科学分野の研究活動」には該当しないので、注意が必要です。
※産学連携に係る共同研究等では、研究が特定の製品への応用を目的としているケースなど、この例外に該当しない場合が多くありますので、注意が必要です。
許可例外が適用できる例とできない例
| 第9条第2項 | 適用できる例 | 適用できない例 | |
|---|---|---|---|
| 第9号 公知の技術 |
イ、ロ、ハ 公知の技術を提供する取引、不特定多数の者が入手、聴講可な技術を取引 |
Web上で公開されている「取扱説明書」 (該当技術を含んでいても適用可) |
アクセス時に(会員)などの認証を行うインターネット、イントラネット上に掲載される技術 |
| 二 ソースコードが公開されているプログラム |
該当技術を含むオープンソースソフトウエア(OSS)を自社製品に組み込んで提供 | OSSの一部を改変後 改変後のソースコードを公開しないで、このOSSを組み込んで提供 |
|
| ホ 技術を公開することを目的とする取引 |
学会事務局に送る論文、編集者に提供する雑誌記事原稿 | 特定の会員に提供される雑誌への投稿記事 翻訳のために送る雑誌原稿 |
|
| 第10号 基礎科学 |
代数学、幾何学 | 計算機科学 | |
| 第11号 工業所有権 |
出願のために送る文書 | 係争のために送る文書の一部 | |
貨物の輸出に関する例外 例外が認められると思われるケースでも必ず事前確認が必要です。
・無償特例 無償で輸入し無償で返送する特定の貨物又は後日無償で輸入する予定で無償で輸出する特定の貨物
(修理,修理のための交換などを想定)
・少額特例 貨物の種類ごとに定められた一定の価格以内の貨物
・部分品特例 輸出する貨物のごく一部として、規制対象となる貨物が組み込まれている場合
許可例外に関するQ&A 例外が認められると思われるケースでも必ず事前確認が必要です。
| Q | A |
| 市販された教科書を用いるなど、公表された情報を用いて行う留学生等の非居住者を対象とする講義や実習に、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用は可能でしょうか。 | 市販された教科書や公表された情報については、既に不特定多数の者に対して公開されている技術に当たると思われ、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の対象となります。しかしながら、それらを用いて講義や実習を行う際に、その内容に公開されていない情報、技術等が含まれていないか事前に確認が必要です。 |
| 大学等が、不特定多数の者を対象とするオンライン講座を行う場合、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用は可能でしょうか。また、聴講者に対し、特定の聴講資格を設けているオンライン講座の場合には、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用は可能でしょうか。 | 特定の聴講資格を設けず、大学等の在学生だけでなく、聴講を希望する者は誰もが参加することができる不特定多数の者を対象としているオンライン講座については、不特定多数の者が入手又は聴講可能な講演会等と同等のものと考えられるため、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用は可能と考えられます。また、聴講者に対し、特定の聴講資格を設けているオンライン講座の場合に は、一般的に、不特定多数の者が入手又は聴講可能な講演会等とは異なり、特定の者に対する技術の提供と同等と考えられることから、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用はできないと考えられます。例えば、在学生のみが聴講可能なオンライン講座は、一般的に、特定の聴講資格を設けているオンライン講座に当たり、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用はできないと考えられます。ただし、オンライン講座で提供する技術内容そのものが既に不特定多数の者に対して公開されている技術であれば、特定聴講資格者であっても貿易外省令第9条第2項第九号の特例の適用は可能と考えられます。 |
| 研究成果などを公知とするための目的で、学会などで発表することもありますが、この場合、貿易外省令第9条第2項第九号の適用は可能でしょうか。また、上記の学会で発表した際の質疑・応答の内容も、同様に貿易外省令第9条第2項第九号の適用は可能でしょうか。 | 研究成果などに係る技術を学会などの場を通じて、不特定多数の者が入手又 は閲覧可能とすることを目的とするものであれば、貿易外省令第9条第2項第九号の特例の対象となります。また、当該学会での質疑・応答の内容については、 公知とするために発表した技術の範囲内であれば、同様に貿易外省令第9条第 2項第九号の特例の対象と考えられます。 |
| 学会用の原稿を送付する場合は許可不要ということですが、機微なものでもよいのでしょうか。 | 不特定多数の者が入手又は閲覧可能とするために論文発表や学会発表などで公表することは、技術を公知とするための技術提供に当たるため、それがリスト規制に該当する技術であったとしても役務許可を取得する必要はありません。ただし、学会参加者に守秘義務を課して発表を行う場合など、すべてが技術を公知とするための技術提供であると必ずしもいえるわけではなく、特例に当たらない場合は役務許可を取得する必要があります(貿易外省令第9条第2項第九号)。その他、法令上の義務ではありませんが、一般公開を検討している原稿の中には大量破壊兵器の開発などにも転用可能な技術情報が含まれている場合もあるため、大量破壊兵器の拡散を防止するという社会的な側面、科学者倫理に基づく側面も ご配慮いただき、一般公開の適否を慎重に検討していただくようお願いいたします。 |
| 特許情報を提供する場合、許可を取らなくてもいいのでしょうか。 | 公開特許情報は「公知の技術」に当たり、役務許可を取得する必要はありません(貿易外省令第9条第2項第九号)。 |
| 非居住者に技術提供する際、最初に公知の特例を検討して、それが公知の技 術であると確認出来た場合は、該非判定をしなくても良いでしょうか。 | 提供予定の技術が貿易外省令第9条第2項第九号の要件を満たす可能性が高い場合には、該非確認より先に特例の適用について検討し、その結果、要件を満たしていることが確認できれば、該非確認を行うことなく、当該技術を提供しても問題ありません。 |